
退職1ヶ月前に伝えたら怒られた…そんな状況に悩んでいませんか?
本来、退職は個人の自由であり、法律的にも1ヶ月前の申し出は問題ない。
しかし、職場によっては「急すぎる」「迷惑だ」と上司から怒られることもある。
特に退職1ヶ月前は辛いと感じる人が多く、引き止めがしつこいケースや気まずい空気に悩まされることもある。
また、就業規則と法律の違いを知らないと、会社側のルールを押し付けられ、不利益を被る可能性もある。
退職の1ヶ月前の報告は遅いのか?適切なタイミングは?
退職1ヶ月前に有給を取得できるのか?
退職の意向をLINEで伝えるのはあり?
こうした疑問や不安を解消するために、この記事では「退職1ヶ月前に伝えたら怒られた理由」と「円満退職に向けた対応策」を詳しく解説する。
スムーズに退職するためのポイントを押さえ、後悔のない決断をしよう。
この記事では下記の内容を知ることができます
- 退職を1ヶ月前に伝えた際に怒られる理由とその背景
- 退職の申し出に関する法律と就業規則の違い
- 退職の1ヶ月前の適切な対応と円満退職のコツ
- 退職をスムーズに進めるための引き継ぎや有給取得のポイント
こちらもCHECK
-

-
第二新卒の人生終了は本当か?転職成功のポイントを解説
「第二新卒 人生終了」と検索し、不安を感じている人は少なくない。 新卒で入社した会社を短期間で辞めたことで、今後のキャリアに自信を持てなくなっているかもしれない。 しかし、第二新卒だからといって人生が ...
続きを見る
-

-
参考転職スクールの評判を徹底解説!未経験20代でも安心の理由
転職を考えている20代の中には、「未経験でも転職できるのか?」と不安を感じている人も多い。 そんな中、近年注目を集めているのが転職スクールだ。 しかし、「転職スクールの評判は本当に良いのか?」「未経験 ...
続きを見る
退職を1ヶ月前に伝えたら怒られた!その理由と対応策
- 1ヶ月前に退職を伝えることはできますか?
- 1ヶ月前に辞めたいのですが、辞められますか?
- 退職の1ヶ月前の報告は遅い?適切なタイミングとは
- 就業規則と法律の違いを理解する
- 退職の1ヶ月前に有給は取得できるのか?
- 公務員のルールは異なる?
- 退職の1ヶ月前は辛い…精神的な負担を軽減する方法
1ヶ月前に退職を伝えることはできますか?

結論として、退職を1ヶ月前に伝えることは可能です。
法律上は、民法627条により、退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば退職できるとされています。
そのため、1ヶ月前に伝えることは十分に余裕を持った対応と言えます。
ただし、会社の就業規則によっては「1ヶ月前までに申告すること」などのルールが定められている場合があります。
このため、事前に就業規則を確認し、会社のルールを守ることが円満な退職につながります。
また、会社によっては引き継ぎや後任の確保に時間がかかるため、1ヶ月前の報告でも「遅い」と感じる職場もあるかもしれません。
特に繁忙期や重要なプロジェクトの最中に退職を申し出ると、上司が強く反発することがあります。
注意ポイント
- 就業規則の確認:退職の申し出期限が決まっている場合がある
- 繁忙期の考慮:退職のタイミングによっては会社に迷惑をかける可能性がある
- 引き継ぎの準備:業務の引き継ぎがスムーズに進むように計画を立てる
以上の点を踏まえ、1ヶ月前に退職を伝えることは問題ありませんが、会社や職場の状況に応じて適切なタイミングを見極めることが重要です。
1ヶ月前に辞めたいのですが、辞められますか?
1ヶ月前に退職することは可能ですが、会社の対応によってスムーズに進まないことがあります。
法律上は2週間前の申告で退職は成立するため、1ヶ月前の申し出は問題ありません。
しかし、会社の就業規則に「〇ヶ月前までに報告すること」と記載がある場合、それに従うのが一般的です。
ただし、以下のようなケースでは、1ヶ月前に辞めることが難しくなる場合があります。
1ヶ月前に辞めるのが難しいケース
- 引き継ぎが終わらない場合:後任が決まっておらず、業務の引き継ぎが進まない
- 繁忙期にあたる場合:忙しい時期に退職を申し出ると引き止められる可能性が高い
- 上司や会社が強く反対する場合:退職を受け入れない態度をとられる
スムーズに1ヶ月後に退職するためのポイント
- 退職届を正式に提出する:口頭ではなく、書面で退職の意思を伝える
- 引き継ぎ計画を作る:業務リストを作成し、後任がスムーズに業務を引き継げるよう準備する
- 有給休暇の取得を考える:1ヶ月前に有給消化を申請すれば、実際の出勤日を減らすことが可能
会社が退職を認めない場合や、強く引き止められる場合は、退職代行サービスを利用することも選択肢の一つです。
また、精神的に追い詰められている場合は、労働基準監督署や弁護士に相談するのも有効な方法です。
退職の1ヶ月前の報告は遅い?適切なタイミングとは

退職を1ヶ月前に報告することは、一般的には適切なタイミングとされています。
多くの企業では、就業規則に「1ヶ月前までに退職の意思を伝えること」と定めており、法律上も問題ありません。
ただし、職場の環境や業務内容によっては、1ヶ月前の報告では「遅い」と思われることもあります。
1ヶ月前の退職報告が遅いとされるケース
- 業務が属人化している:専門知識が必要な業務で、後任の育成に時間がかかる
- 繁忙期やプロジェクトの最中:退職によって業務が滞る可能性がある
- 人手不足の職場:退職後の人員補充が難しく、残された従業員の負担が増える
適切な退職のタイミングとは?
退職のタイミングは、会社の業務状況や職場の慣習を考慮することが重要です。
以下のポイントを押さえて、適切なタイミングを決めましょう。
- 就業規則の確認:退職の申し出期限を守る
- 引き継ぎのスケジュールを考える:後任者が決まるまでの期間を見積もる
- 転職先との調整を行う:次の職場の入社日を考慮し、余裕を持って辞める
理想的な退職の申告時期
- 2〜3ヶ月前:余裕を持って引き継ぎができるため、円満退職しやすい
- 1ヶ月前:多くの会社で認められる一般的な期間
- 2週間前:法律上は問題ないが、引き継ぎが間に合わず、トラブルになる可能性がある
退職の1ヶ月前の報告が遅いかどうかは、職場の状況によって変わります。
スムーズに退職するためには、できるだけ早めに準備を始め、計画的に行動することが大切です。
就業規則と法律の違いを理解する
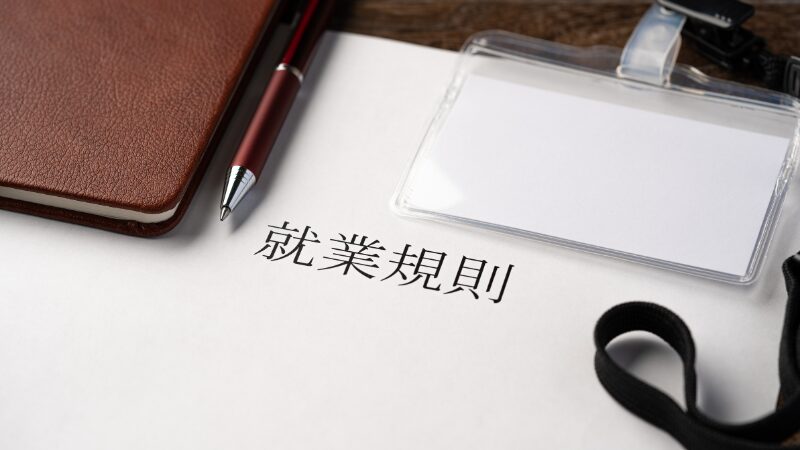
退職を考える際、「就業規則」と「法律」 の違いを正しく理解しておくことが重要です。
特に退職時のルールは会社ごとに異なるため、誤解が生じやすいポイントです。
就業規則とは?
就業規則は、会社が定めた職場のルールです。
労働時間や休暇、退職手続きの流れなどが記載されており、社員はこれに従うことが基本とされています。
ただし、就業規則は法律よりも優先されるわけではありません。
法律に違反する内容が含まれている場合、その部分は無効となります。
法律とは?
退職に関する法律は、民法や労働基準法 によって定められています。
たとえば、民法627条 では「退職の申し出をしてから2週間が経過すれば退職できる」と規定されています。
これは法律として定められた最低限のルールであり、会社の就業規則がこれより厳しくても法的拘束力はありません。
就業規則と法律、どちらが優先される?
基本的には、法律が最優先されます。
たとえば、就業規則に「退職の申し出は3ヶ月前までに行うこと」と書かれていたとしても、法律上は2週間前の通知で退職が可能 です。
ただし、会社とのトラブルを避けるためには、なるべく就業規則を尊重して対応することが望ましいでしょう。
就業規則と法律の違いを理解するポイント
- 法律が最優先されるが、円満退職のためには就業規則も考慮する
- 就業規則の内容が法律に反する場合、その部分は無効
- 退職の申し出期間や手続きは、法律と就業規則の両方を確認することが重要
会社側が法律に違反して強制的に退職を引き延ばそうとする場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することも視野に入れておきましょう。
退職の1ヶ月前に有給は取得できるのか?
結論として、退職の1ヶ月前でも有給休暇の取得は可能です。
有給休暇は労働基準法で認められた労働者の権利 であり、退職間際だからといって会社が拒否することはできません。
法律上のルール
労働基準法では、「有給休暇は労働者が自由に取得できる」 と定められています。
そのため、退職の1ヶ月前であっても、有給を消化することは法律上問題ありません。
ただし、会社には「時季変更権」という権利があり、業務に大きな支障が出る場合に限り、有給の取得日を変更するよう求めることができます。
しかし、退職日が確定している場合、会社が時季変更権を行使することはほぼ不可能です。
会社が有給を認めない場合の対処法
一部の企業では、「退職前の有給取得は認めない」 というルールを独自に設けていることがあります。
しかし、これは法律違反であり、会社の方針に従う必要はありません。
もし上司が有給申請を却下したり、圧力をかけて取得を妨げたりする場合は、以下の対応を検討しましょう。
- 就業規則を確認する(有給の申請ルールをチェックする)
- 退職願と同時に有給届を提出する(書面で記録を残す)
- 労働基準監督署に相談する(違法な対応を報告する)
- 退職代行を利用する(スムーズに退職手続きを進める)
退職前の有給消化のポイント
- 取得可能な有給日数を事前に確認する
- できるだけ早めに申請し、引き継ぎに影響が出ないよう配慮する
- 会社が認めない場合は、労働基準監督署に相談する
有給休暇は、これまで働いてきた労働者の正当な権利です。
退職の1ヶ月前でも、適切な手続きを踏めば取得できるので、安心して申請しましょう。
公務員のルールは異なる?

公務員の退職ルールは、民間企業とは異なる点が多くあります。
法律や職務の性質上、退職の手続きが厳格に決められているため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
公務員の退職ルールの基本
公務員が退職する場合、「地方公務員法」や「国家公務員法」 に基づいて手続きが進められます。
一般的に、退職の申し出は1ヶ月以上前に行うことが推奨される ため、民間企業のように2週間前で退職するのは難しいケースが多いです。
また、公務員は「辞職願(退職願)」を提出しても、承認されるまで辞めることができません。
これは、職務の引き継ぎや業務の安定性を確保するための措置です。
公務員が退職する際のポイント
- 退職の1ヶ月以上前に申し出るのが一般的
- 辞職願(退職願)は上司の承認が必要
- 退職日を調整する必要があるため、早めの相談が重要
特に、教員や警察官などの特殊な職種では、さらに厳しいルールが適用されることがあります。
引き継ぎの都合で、実際には3ヶ月前以上の申し出が求められる場合もある ため、勤務先の規定を事前に確認しましょう。
公務員の退職で注意すべき点
- 自己都合退職の場合、退職金の支給額が変わる可能性がある
- 有給休暇の消化についても、所属機関の許可が必要になる
- 次の就職先によっては、公務員の副業規定が影響することもある
公務員の退職は、民間企業よりも慎重に進める必要があります。
退職を考えたら、なるべく早めに直属の上司に相談し、手続きの流れを確認することが重要です。
退職の1ヶ月前は辛い…精神的な負担を軽減する方法
退職の1ヶ月前は、職場での気まずさや上司からの引き止めなどで、精神的に辛くなることがあります。
特に、長年勤めた会社を辞める場合や、上司の反応が厳しいと感じる場合、ストレスが大きくなるでしょう。
ここでは、退職前の精神的な負担を軽減する方法を紹介します。
1. 退職までのスケジュールを明確にする
退職が決まったら、最終出勤日や有給消化の計画を立てる ことで、精神的な負担を軽くできます。
具体的には、以下のようなスケジュールを作ると良いでしょう。
- 退職届の提出日
- 引き継ぎ業務の期限
- 最終出勤日と有給消化の開始日
- 退職後の手続き(健康保険・年金の変更など)
退職の流れを把握することで、「まだ何をすればいいのかわからない」という不安を減らせます。
2. 周囲の反応を気にしすぎない
退職を伝えると、職場の上司や同僚の反応が気になり、気まずさを感じることがあります。
しかし、退職は個人の自由であり、誰にも止める権利はありません。
以下のような言葉をかけられることもありますが、気にする必要はありません。
- 「この忙しい時期に辞めるの?」
- 「みんなに迷惑をかけることを考えてほしい」
- 「もう少し早く言ってくれたらよかったのに」
こうした発言は、一時的な感情 から出るものであり、時間が経てば解消されることがほとんどです。
気にしすぎず、「自分の決断に自信を持つこと」が大切です。
3. 退職後の楽しみを考える
退職が決まると、どうしても「今の職場のことばかり考えてしまう」 という人が多いです。
しかし、それでは不安やストレスが大きくなってしまいます。
そこで、退職後の新しい生活や転職先での目標を考える ことで、前向きな気持ちになれるでしょう。
例えば、
- 転職先で挑戦したいことをリストアップする
- 退職後の旅行や趣味の計画を立てる
- 新しい環境での人間関係を楽しみにする
退職は、人生の新たなスタート です。
未来に目を向けることで、気持ちが軽くなることもあります。
4. 退職代行を検討する
もし、上司の引き止めがしつこかったり、精神的な負担が大きすぎたりする場合は、退職代行を利用する のも一つの方法です。
退職代行を使えば、会社と直接やりとりせずに退職手続きを進めることができます。
退職代行のメリットは以下の通りです。
- 上司と直接話さずに済むため、精神的なストレスを減らせる
- 退職手続きがスムーズに進む
- 有給消化や未払い給与の交渉も代行してもらえることがある
ただし、退職代行を利用すると、会社の同僚と直接話す機会がなくなるため、「最後にきちんと挨拶をしたかった」と後悔する可能性もあります。
そのため、自分にとって最適な方法かどうか、事前にしっかり検討しましょう。
退職1ヶ月前の辛さを乗り越えるには?
- 退職スケジュールを明確にして、不安を減らす
- 周囲の反応を気にしすぎず、自分の決断に自信を持つ
- 退職後の楽しみを考え、前向きな気持ちを保つ
- どうしても辛い場合は、退職代行の利用を検討する
退職の1ヶ月前は、気まずさやストレスを感じることが多いですが、工夫次第で精神的な負担を軽減できます。
自分の気持ちを大切にしながら、退職準備を進めましょう。
退職を1ヶ月前に伝えたら怒られた!スムーズに辞める方法
- 1ヶ月前に退職伝えるときの注意点
- 退職する最悪のタイミングはいつですか?
- 会社を辞めるのは何ヶ月前が常識?
- 退職の意向はラインで挨拶はあり?適切な伝え方
- 退職までの期間が気まずい…どう乗り越える?
- 退職の引き止めがしつこい場合の対処法
- 退職日とは?法律上のルールを解説
- 転職エージェントを活用して円満退職を目指そう
1ヶ月前に退職伝えるときの注意点

退職を1ヶ月前に伝えることは法律上問題ありませんが、スムーズに進めるためにはいくつかの注意点があります。
会社の状況や上司の反応を考慮しながら、適切な対応を心がけましょう。
1. 退職の意志をできるだけ早めに伝える
法律上は2週間前の申告でも問題ありませんが、会社によっては1ヶ月前の申告が必要な場合があります。
また、職場の雰囲気によっては「最低でも2〜3ヶ月前に言うべき」という暗黙のルールがあることもあります。
円満退職を目指すなら、就業規則を確認した上で、早めに上司に相談するのがベストです。
2. 退職理由は簡潔かつ前向きに伝える
退職を伝えるときは、理由を明確にしておくことが重要です。
ネガティブな理由(人間関係の不満や給与への不満など)は避け、前向きな理由を伝えましょう。
例:
- 「キャリアアップのため、新しい挑戦をしたいと考えています。」
- 「家庭の事情で、勤務環境を変える必要がありました。」
上司に余計な詮索をされずに済み、スムーズに退職を進めることができます。
3. 退職届を提出し、書面で証拠を残す
口頭で退職の意思を伝えた場合、上司の判断で「言っていないことにされる」リスクもあります。
そのため、退職届を正式に提出し、証拠を残すことが大切です。
また、メールでの報告も有効ですが、会社の規定に従いましょう。
4. 引き継ぎ計画を事前に準備する
上司に退職を伝える際、「業務の引き継ぎはどうするのか?」と聞かれることがほとんどです。
退職日までに業務を整理し、誰に何を引き継ぐかを事前に考えておきましょう。
具体的には、以下のような対応が必要です。
- 業務のマニュアルを作成する
- 後任者が決まっている場合は、引き継ぎのスケジュールを組む
- クライアントや取引先に迷惑をかけないよう、事前に報告しておく
5. 有給休暇の取得は計画的に進める
退職前に有給休暇を取得する場合、事前に申請し、上司と調整しておくことが必要です。
法律上、有給休暇の取得は労働者の権利ですが、職場によっては「繁忙期だから休むな」と反対されることもあります。
スムーズに退職するためには、有給休暇の取得を希望する場合は早めに相談し、計画的に進めましょう。
退職する最悪のタイミングはいつですか?
退職する際、タイミングを間違えると職場の雰囲気が悪くなり、転職活動にも悪影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、退職に適さないタイミングについて解説します。
1. 繁忙期のど真ん中
職場が最も忙しい時期に退職を申し出ると、上司や同僚から反発される可能性が高くなります。
例えば、以下のような時期は避けたほうが無難です。
- 決算期(多くの企業では3月や9月)
- 年末年始前後(12月・1月)
- 会社の大きなプロジェクトやイベントの直前
この時期に退職を申し出ると、職場の負担が増え、不満を持たれやすくなります。
2. 上司や人事担当が不在のとき
上司が長期出張や休暇中のタイミングで退職を申し出ると、対応が後回しにされることがあります。
また、人事部が忙しい時期(新卒採用の準備期間など)も、スムーズに手続きが進まない可能性が高いです。
そのため、上司が落ち着いている時期を狙って相談するのがベストです。
3. 昇進やボーナス直前のタイミング
退職の時期によっては、昇進やボーナスの支給対象から外されることもあります。
例えば、ボーナスの支給基準が「支給日まで在籍していること」になっている場合、支給直前に退職するとボーナスがもらえません。
会社の就業規則を確認し、損をしないように退職時期を調整しましょう。
4. 内定が決まっていない状態
転職活動を始める前に退職を決めてしまうと、次の仕事が見つかるまで収入がなくなります。
焦って転職先を決めることになり、条件の良くない会社に入社してしまうリスクもあります。
退職を考える際は、事前に転職活動を進めておくことが重要です。
会社を辞めるのは何ヶ月前が常識?
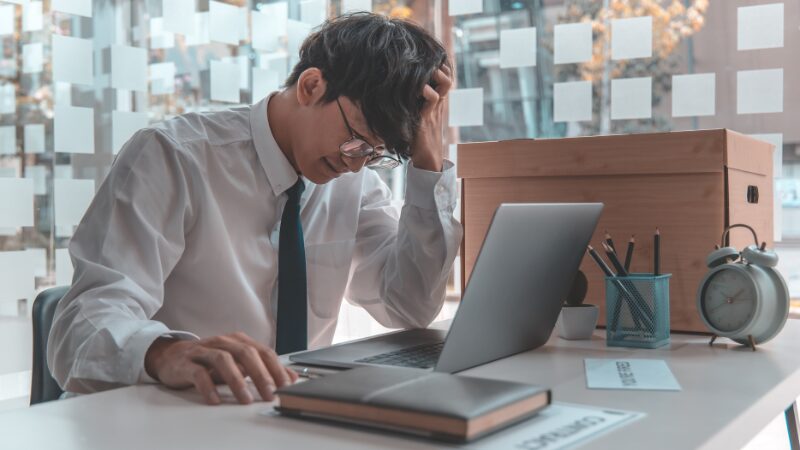
退職の申し出は、何ヶ月前に伝えるのが一般的なのでしょうか?
会社や業界によって異なりますが、一般的な基準を紹介します。
1. 法律上は2週間前でもOK
民法627条では、労働者は退職の意思を示してから2週間後に退職できると定められています。
そのため、極端な話、2週間前に伝えれば法律上は問題ありません。
しかし、実際には就業規則や職場の慣習を考慮する必要があります。
2. 一般的には1〜3ヶ月前が理想
多くの企業では、就業規則で「退職の申し出は1ヶ月前まで」と定めているケースが多いです。
ただし、業務の引き継ぎや人材補充の関係から、以下の目安で申し出るのが一般的です。
- 一般職(事務職・営業職など) → 1〜2ヶ月前
- 管理職・専門職(エンジニア・研究職など) → 2〜3ヶ月前
- プロジェクトを担当している場合 → プロジェクトの終了を考慮する
3. 退職を伝えるタイミングのポイント
- 会社の就業規則を確認し、決められた期間内に伝える
- 上司が忙しくないタイミングを選ぶ
- 円満退職を目指すなら、余裕を持って早めに伝える
一般的には1〜3ヶ月前の報告が適切ですが、職場の状況に応じて判断しましょう。
また、次の仕事が決まっていない場合は、退職のタイミングを慎重に決めることが重要です。
退職の意向はラインで挨拶はあり?適切な伝え方

退職の意向をLINEで伝えることは、基本的には避けたほうが良いです。
LINEは気軽にやり取りできるツールですが、ビジネス上の正式な連絡手段として適しているとは言えません。
特に、退職のような重要な話題は、直接伝えるか書面で提出するのが一般的です。
1. 退職の意向を伝える適切な方法
退職を伝える際は、以下の方法が望ましいです。
- 直接、上司に伝える(対面が理想)
- 上司が忙しい場合は、電話でアポイントを取る
- 正式に退職届を提出する(口頭だけではなく書面も重要)
LINEはあくまでもカジュアルなツールのため、「退職の話をしたいのでお時間いただけますか?」 と事前連絡をする程度に留めておきましょう。
2. 退職時のLINEでの挨拶はOK?
退職日が近づいたら、お世話になった同僚や関係者にLINEで挨拶をするのは問題ありません。
ただし、内容には注意が必要です。
メモ
適切なLINEの挨拶例:
「お疲れ様です。○○です。
このたび、○月○日をもって退職することになりました。
これまで大変お世話になり、本当にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします!」
参考
避けたほうがいい表現:
- 「急ですみませんが、辞めることになりました!」(軽すぎる)
- 「いろいろありましたが、お世話になりました」(トラブルを匂わせる)
円満に退職するためにも、相手が不快にならないような言葉選びを心がけましょう。
退職までの期間が気まずい…どう乗り越える?
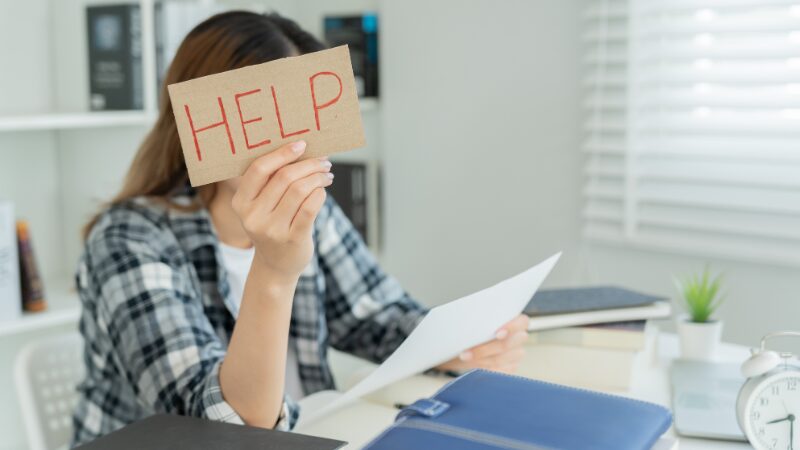
退職を申し出た後、最終出勤日までの期間が気まずく感じることは少なくありません。
周囲の視線や引き継ぎのプレッシャーなど、ストレスを感じる要因はいくつもあります。
しかし、適切な対策を取れば、気まずさを最小限に抑えられます。
1. 退職日までのスケジュールを明確にする
不安を減らすためには、退職までの流れをしっかり整理しておくことが重要です。
- 引き継ぎ業務のスケジュールを作成する
- 必要な書類やマニュアルを整える
- 周囲に迷惑をかけないよう、業務を計画的に進める
計画的に進めることで、自分の気持ちも落ち着き、職場でのストレスを軽減できます。
2. 必要以上に気を遣いすぎない
退職を決めたことで、周囲の反応が気になるかもしれません。
しかし、気を遣いすぎると、余計に疲れてしまいます。
- 無理に話しかけようとしない
- 退職の話題ばかりしない
- 必要な業務に集中する
自分のペースで仕事を進めることで、気まずさを感じる時間を減らせます。
3. 前向きな気持ちを持つ
退職は、新しい環境へ向かうための大事なステップです。
今の職場での時間を無駄にしないよう、最後まで誠実に働くことを意識しましょう。
また、退職後の新しい生活を考えることで、前向きな気持ちを持つことができます。
- 「新しい職場でどんなことを学べるか?」
- 「今後どんなキャリアを築きたいか?」
こうしたことを考えながら過ごせば、気まずさも気にならなくなるでしょう。
退職の引き止めがしつこい場合の対処法
退職の意向を伝えたあと、しつこく引き止められることはよくあります。
特に、会社側にとって必要な人材であればあるほど、強く引き止められる可能性が高くなります。
1. 退職の意志を明確に伝える
引き止めがしつこい場合、まずは「退職の意志が変わらないこと」をはっきり伝えることが重要です。
参考
例:
「大変お世話になりましたが、○月○日で退職する意志は変わりません。」
遠回しな表現を使うと、会社側が「まだ交渉の余地がある」と思ってしまいます。
毅然とした態度で伝えましょう。
2. 感情的にならず、冷静に対応する
上司によっては、感情的になって怒ったり、脅したりすることもあります。
しかし、こちらが冷静に対応すれば、相手も落ち着きを取り戻すことが多いです。
- 「決断に時間をかけて考えましたので、変更するつもりはありません。」
- 「転職先とすでに契約を結んでおり、予定を変えることはできません。」
こうした冷静な対応を続けることで、無理な引き止めを減らすことができます。
3. 引き止めの理由を見極める
引き止められる理由には、主に以下のようなものがあります。
- 会社にとって貴重な人材だから → 後任の確保が難しい
- 人手不足で困るから → 退職を遅らせようとする
- 単なる引き止めの習慣 → 本心ではなく、形だけの引き止め
引き止めの理由が「単なる引き止めの習慣」なら、毅然とした態度で対応すればすぐに受け入れられます。
しかし、「後任が見つかっていない」などの理由で引き止められる場合は、引き継ぎのスケジュールをしっかり決めて進めるとスムーズに退職できます。
4. どうしても辞められないなら退職代行を利用する
会社が強引に引き止めたり、嫌がらせをしてくる場合は、退職代行サービスを利用するのも一つの方法です。
退職代行を利用すると、自分で退職の手続きをする必要がなく、会社と直接やり取りをしなくても辞めることができます。
精神的に辛い場合は、無理せず専門家に相談しましょう。
ポイント
引き止めがしつこい場合の対処法
- 退職の意志は明確に伝える
- 感情的にならず、冷静に対応する
- 引き止めの理由を見極め、適切に対応する
- どうしても辞められない場合は退職代行を検討する
強引な引き止めに屈せず、自分のキャリアを優先して行動することが大切です。
一度決めた退職の意志をしっかり貫きましょう。
退職日とは?法律上のルールを解説

退職日とは、雇用契約が正式に終了する日を指します。
この日は、会社での勤務が終わる日ではなく、雇用関係が完全に解消される日 であるため、退職届を出した日や最終出勤日とは異なる点に注意が必要です。
1. 退職日の法律上のルール
退職日は、主に 「自己都合退職」 と 「会社都合退職」 のどちらかによって決まります。
-
自己都合退職の場合
民法627条により、労働者が退職を申し出てから2週間後には退職が可能 です。
ただし、会社の就業規則で「1ヶ月前に申し出ること」と決まっているケースもあるため、事前に確認しておきましょう。 -
会社都合退職の場合
会社側から解雇される場合、労働基準法20条により、少なくとも30日前に解雇予告をする義務があります。
もし30日以内に解雇される場合は、解雇予告手当(30日分の給与) が支払われるのが基本ルールです。
2. 退職日の決め方と注意点
退職日は、企業との話し合いのもと決まることが多いですが、以下の点に注意しましょう。
-
最終出勤日と退職日は別になることがある
有給休暇を消化する場合、最終出勤日よりも後に退職日が設定されることがあります。 -
退職日を基準に社会保険や税金の手続きが行われる
退職日が月の途中か月末かで、社会保険料の負担が変わることがあるため、退職時期の調整も重要です。 -
転職先の入社日と調整する
転職する場合は、次の会社の入社日と退職日を調整し、空白期間を作らないようにする ことも大切です。
3. 退職日を決める際に確認すべきポイント
- 就業規則に退職日の規定があるか?
- 有給休暇の消化をどうするか?
- 次の仕事のスケジュールと調整できているか?
- 退職後の社会保険や年金の手続きはどうするか?
退職日は単なる「最後の出勤日」ではなく、その後の生活にも影響を与える重要な日です。
退職手続きを進める際は、会社のルールや法律を理解し、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
転職エージェントを活用して円満退職を目指そう

転職エージェントを利用することで、退職の準備をスムーズに進め、円満退職につなげることができます。
特に、転職活動と退職手続きを並行して行う場合、プロのサポートを受けることで、負担を軽減できます。
1. 転職エージェントを活用するメリット
転職エージェントを利用すると、以下のようなメリットがあります。
-
円滑に転職活動を進められる
退職後に焦って転職先を探すのではなく、在職中に転職先を決めることができる ため、経済的な不安が少なくなります。 -
退職のタイミングを相談できる
転職エージェントは、新しい職場への入社時期の調整 もサポートしてくれるため、退職日との兼ね合いを考慮しながら進められます。 -
退職のアドバイスが受けられる
「退職を伝えるタイミング」や「引き継ぎの進め方」など、円満退職に向けた具体的なアドバイスをもらうことができる ため、職場とのトラブルを防ぐことができます。
2. 転職エージェントを利用した退職の流れ
- 転職エージェントに登録し、キャリアカウンセリングを受ける
- 求人紹介を受けながら転職活動を進める
- 内定をもらったら、退職の準備を開始する
- 転職エージェントと相談し、円満退職に向けたスケジュールを立てる
- 引き継ぎを行い、スムーズに退職する
3. 転職エージェントを活用する際のポイント
- 退職を考えていることを、社内でむやみに話さない
- 転職先と退職日をしっかり調整する
- 有給休暇の取得や手続きについて事前に確認しておく
転職エージェントを活用することで、無駄なトラブルを避け、スムーズな退職が可能になります。
「退職の準備と転職活動を同時に進めたい」という人には、特におすすめの方法です。
円満退職を目指すためにも、転職エージェントのサポートを上手に活用しましょう。
メーカー専門の求人サイト「タイズ」
タイズは2005年創業以来、メーカー特化の転職支援を行い、ダイキン工業やパナソニックなど大手企業との取引実績も豊富。近年はIT領域にも進出し、メーカー×IT転職を強力サポート!
タイズの特長
- 大手メーカーへの支援実績多数
- メーカー専門転職エージェント総合満足度第1位
- 求職者満足度92%の高品質サポート
- 的確な求人提案&高い合格率
第二新卒エージェントneo
第二/既卒/フリーター/中退/高卒の就職・転職支援【第二新卒エージェントneo】
手厚いサポートであなたの転職を支援!
- 平均10時間の個別サポートで安心!
- 企業担当による面談対策&幅広い求人紹介
- 内定後・入社後もフォローで長期的にサポート
- 訪問済み企業のみ紹介だからミスマッチなし
- 不採用時のフィードバックで次のチャンスに活かせる
転職スクール
未経験転職も安心!圧倒的な求人数と手厚いサポート
- 40,000件以上の求人を紹介可能!他社にはない案件も多数
- 未経験OK求人13,500件!不安を解消しながら転職活動
- 専門チームが履歴書・職務経歴書を作成し、高品質な応募書類を準備
- 選考フォローも充実! 面接対策で自己PRを言語化し、成功へ導く
- 書類通過率92.2%、内定率82.7%の実績
- 業界知識が豊富で、適職や働き方の最適ビジョンを提案
- LINEでエージェントに即相談OK!
明光キャリアパートナーズ(エンジニア向け)
年収1,000万円以上の案件多数!安心の転職支援
- 大手からスタートアップまで豊富な紹介実績
- 明光義塾を運営する明光ネットワークジャパンのグループで安心!
- 経験・希望・価値観に合った業種・企業を提案
- 履歴書・面接対策など細かいサポートで成功率UP
まとめ:退職を1ヶ月前に伝えたら怒られた?理由と対策を解説

記事の内容をまとめました
- 退職を1ヶ月前に伝えることは法律上問題ない
- 民法627条では2週間前の申告で退職可能と定められている
- 会社の就業規則で「1ヶ月前までに申告」と定められている場合がある
- 繁忙期やプロジェクトの最中の退職申告は反発されやすい
- 退職を1ヶ月前に伝えると「遅い」と感じる職場もある
- 引き継ぎの準備を怠ると職場の負担が増え、トラブルになりやすい
- 退職の意思は口頭だけでなく書面(退職届)で伝えるのが望ましい
- 退職の理由は前向きなものを伝えるとスムーズに進みやすい
- 退職までの期間を乗り越えるためにはスケジュールを明確にする
- 退職の意思を伝えた後は、職場の雰囲気が気まずくなることが多い
- 有給休暇の消化は法律上可能だが、会社の反発を受けることもある
- 退職時にしつこく引き止められる場合は毅然とした態度で対応する
- 公務員の退職は上司の承認が必要で、手続きが厳格に決められている
- LINEで退職を伝えるのは避けるべきだが、挨拶には適している
- 退職するタイミングは業界や職場によって異なり、事前確認が重要
- 転職エージェントを利用するとスムーズな退職準備が可能になる
- 退職後の生活や転職先の準備を考えることで精神的な負担を減らせる
- 退職代行を利用すれば、会社と直接やり取りせずに退職できる
- 上司が不在のタイミングで退職を伝えると対応が遅れる可能性がある
- ボーナス支給前の退職は損をする可能性があるため注意が必要
- 次の職場の入社日と退職日を調整し、空白期間を作らないようにする
- 退職の意志を伝える際、必要以上に気を遣いすぎないことが大切
- 職場のルールと法律の違いを理解し、適切な手続きを進める
- 退職を申し出るときは、上司が落ち着いている時期を狙うのがベスト
- 退職日と最終出勤日が異なるケースもあるため、事前に確認する
こちらもCHECK
-

-
第二新卒の転職がおすすめな理由と後悔しない選び方のポイント
こんにちは。キャリアブリッジラボ運営者のSです。 今の会社が「なんか違うな」「このままここで働き続けていいのかな」と感じて、第二新卒転職おすすめの情報を探しているあなたへ向けて書いています。第二新卒転 ...
続きを見る